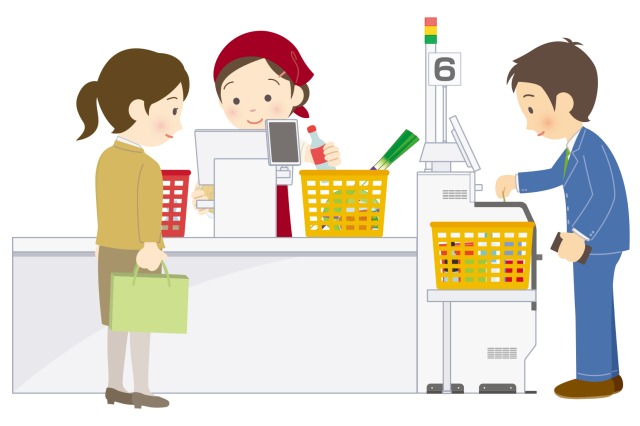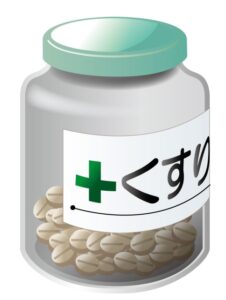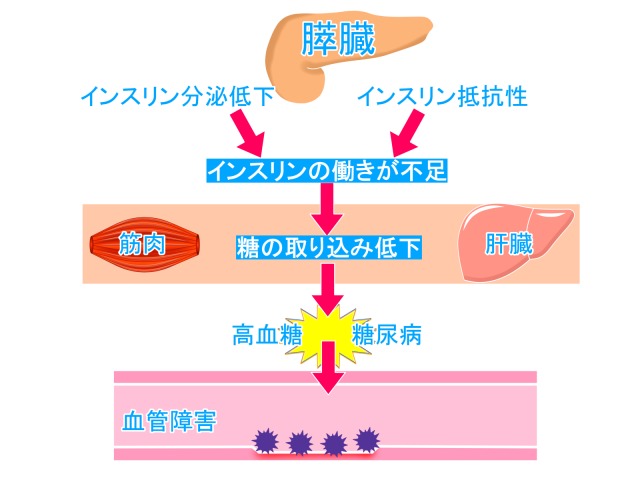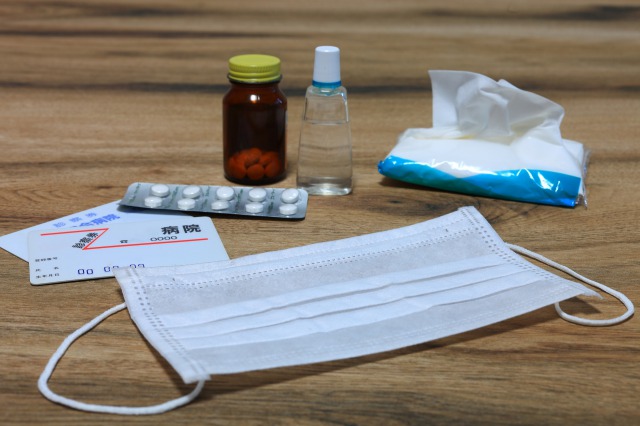前回の続きとして、新人登録販売者が対応に苦労する代表的なケースと、その対応の仕方について、いくつか紹介します。

💊④「一番効く薬はどれですか?」という質問
慢性的な倦怠感や不眠、のぼせ、冷え、立ちくらみ、手足のしびれ、食欲不振、吐気、めまいなど、いわゆる「不定愁訴」と呼ばれる症状は、新人登録販売者にとって苦手な事例の1つです。
不定愁訴への対応では漢方薬を活用することが多くなりますが、店舗によって取り扱うアイテム数に差がありますし、症状の他に飲む人の「証」を確認するなど独持な見方をするので、非常に奥が深い分野です。まずは店舗にある漢方薬の処方の適応症や、配合されている生薬などについて学習していきましょう。
また、「風邪で熱と咳があって、下痢もしている」というように、複数の症状が出ている場合も、お客様の状況を捉えるポイントがわからず対応に困ることがあるでしょう。症状が多い時は、「最もつらい症状」と「2番目につらい症状」を聴き取って、ある程度範囲を絞ってみるとよいでしょう。
症状の見当がつかないのは、病態の知識不足のせいでもあるので、わからなかったことはその都度調べて記録しておきましょう。
💊⑤商品の「効能・効果」に記載されていない症状
添付文書の効能・効果に記載がない症状に対して、その商品をすすめてもよいかどうか迷った経験のある登録販売者も多いと思います。基本的に、添付文書に記載がない使い方はできません。
例えば、「原因のわからないめまいを抑えるために、トラベルミンをおすすめしてもいいか?」という場合、トラベルミンの効能・効果には「乗り物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防緩和」と記載されていますので、乗り物酔いが原因でなければおすすめできません。「めまい」「頭痛」といった症状だけでなく、それが何に由来するものなのかもしっかり確認しましょう。
また、サプリメントの効き目をたずねられることがありますが、サプリメントは効能・効果を謳えないものなので、病気の症状に効果があるというような返答や情報提供はできません。
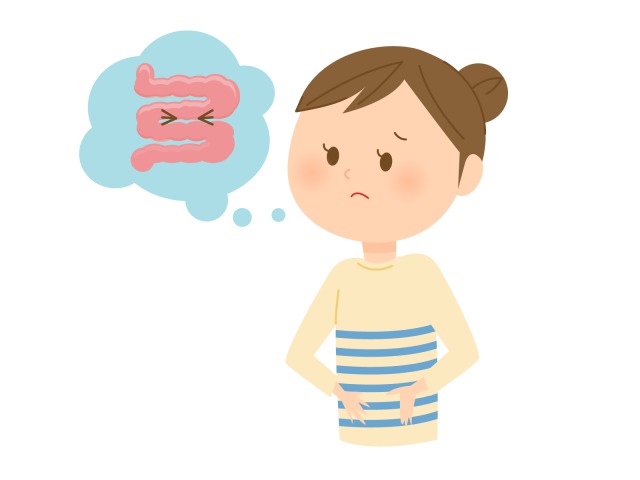
💊⑥特定の薬を長期連用している人への対応
咳止め薬など、濫用のおそれのある成分を配合する商品については、販売の際の本数に制限が設けられています。依存性のある成分が配合された商品を長期にわたって連用していると、本人の意思だけで使用を止めることが難しくなります。登録販売者が店頭で出来ることは限られると思いますが、濫用が疑われる人にはそのリスクを説明する、毅然とした態度で販売を断るなど、店舗としての対応を決めておくとよいでしょう。1人で判断するのではなく、店舗の従業員で統一した対応をとることがポイントです。
咳止め薬以外にも、便秘薬や睡眠改善薬、鼻炎薬、解熱鎮痛剤、総合感冒薬など、市販薬全般で特定の商品を長期間連用している事例に遭遇することが多々あります。対症療法を目的とする市販薬は、基本的には症状がある時に使用するものです。
しかし、「便秘薬を服用しないと排便できなくなった」「点鼻薬をスプレーしてもすぐに鼻がつまる」「風邪薬を毎朝飲まないと気分がスッキリしない」など、さまざまな理由で市販薬を長期連用している人がいます。
心理的な依存などから使用を止められない状態に陥っている人もおり、繰り返し同じ商品を購入する人に対しては、適切なアドバイスが必要でしょう。
「お薬の効き目で、何か困っていることはありませんか?」といった声かけから始める問良いと思います。こちらのアドバイスに耳を貸してもらえないケースもありますが、消費者が安全に市販薬を使用するのをサポートするのが登録販売者の役割。無関心であってはいけません。
そもそも連用によるリスクを知らない人もいるので、症状の聴き取りを行いながら、丁寧に情報提供しましょう。