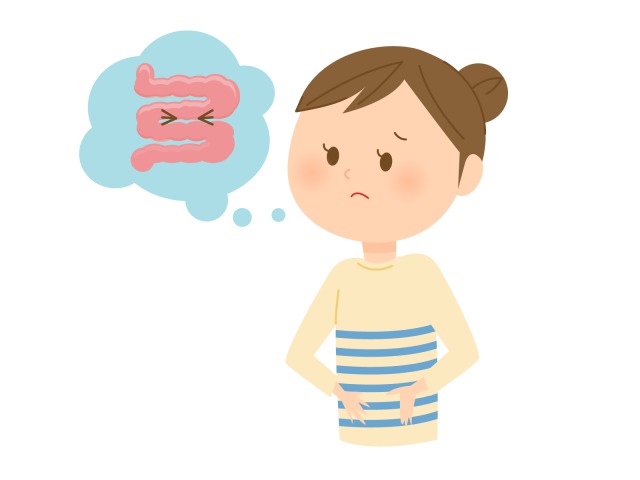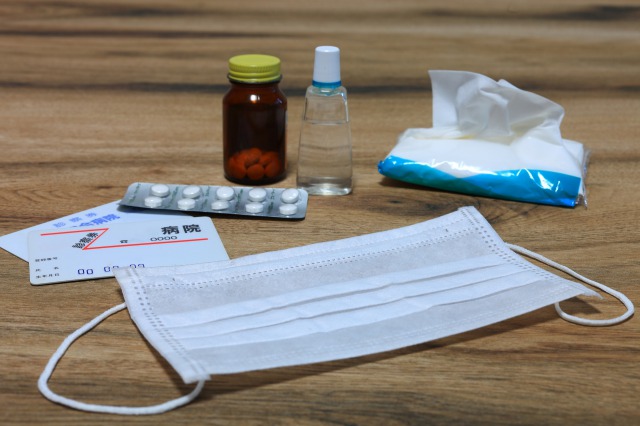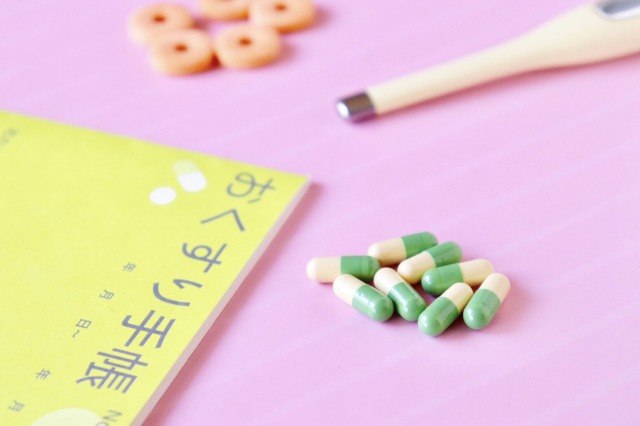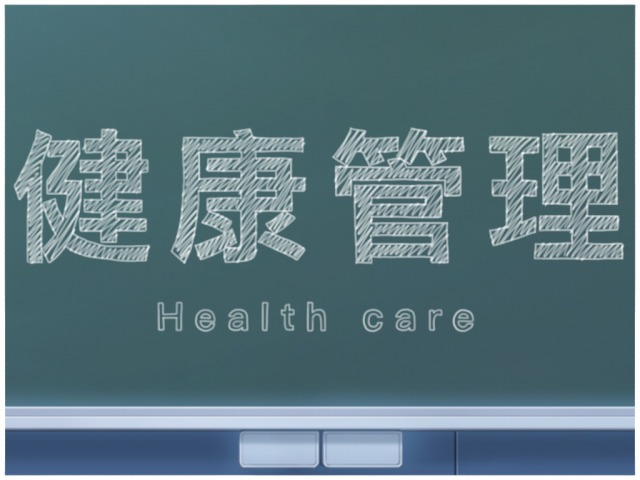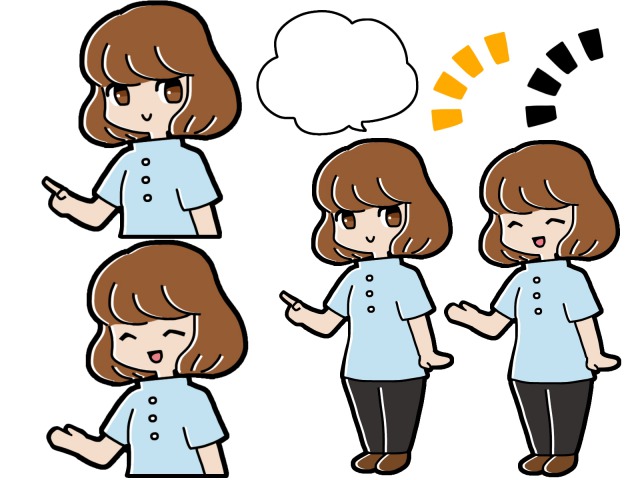「実務期間」の要件は要注意です。
実務(業務)経験の規定には、従事した期間や時間などの要件があります。勤務先のシフトや休職期間なども関わるので、自身の状況を確認するようにしましょう。

実務(業務)経験期間を満たさないと「研修中」のまま
管理者要件を満たす登録販売者(研修中ではない)として勤務するためには、実務経験(もしくは業務経験)条件を常にクリアし続ける必要があります。
2015年以前は、受験前の実務経験条件を満たしていれば、合格後は正規の登録販売者としてずっと働くことができました。しかし、現行の制度では、医薬品販売管理者に従事していた期間によっては「研修中の登録販売者」に戻ってしまうこともあります。
ただし、2015年3月31日までに合格した登録販売者には、「2021年8月1日までは、過去5年以内の業務経験が24か月に満たなくても「管理者要件を満たす登録販売者」とみなす」という経過措置が適用されています。2021年8月2日以降は、経過措置対象の資格者も含めたすべての登録販売者に、以下の管理者要件の実務・業務経験が適用されます。
|
・薬事業務に従事する期間:過去5年以内に通算2年(24か月)以上
・薬事業務に従事する時間:過去5年以内に合計1920時間以上 |
2020年3月27日までは、薬事業務に従事する時間は「ひと月80時間以上」という縛りがありましたが、現在はなくなっています。つまり、業務に従事した期間が過去5年以内に24か月以上あり、累計1920時間以上あれば、管理者要件を満たす実務・業務経験とみなされます。
たとえば、薬事業務に従事した業務が1カ月32時間だった場合は、5年(60か月)1920時間ですから、要件を満たします。月160時間(1日8時間×20日)の実務経験があった場合も12か月で1920時間に到達しますが、「24か月以上」という要件を満たさないので「研修中」のままとなります。なお、登録販売者(研修中含む)として業務に従事した期間と、一般従事者として実務に従事した期間は合算可能です。
「実務(業務)経験」のルールがよくわからない・・・
正規の登録販売者となってからも、業務内容や休職期間によっては、要件を満たさなくなる場合も。業務に従事した時間数は、自身でも管理するようにしましょう。
実務(業務)経験の期間のカウント方法はちょっと複雑
「過去5年以内の実務(業務)経験が24か月以上、かつ1920時間」という条件をクリアし続けることが管理者要件となるわけですが、「経験期間の考え方がわからない」「今従事している仕事が実務(業務)経験として認められるのか?」といった疑問がでてきます。
一人前の登録販売者と思っていたら、実は「研修中」の身分だったでは困りますから、「実務(業務)経験」の定義は気になるところです。
基本的に、実経験(もしくは業務経験)とは、医薬品の販売管理に関わった時間を指しますが、どのような業務がそれに該当するかは、企業ごとに判断するケースがほとんどです。勤務時間数がそのまま「実務(業務)経験」とはならないケースもあるので、自身の実務(業務)経験が規定を満たしているのかは不明な人は、遠慮せずに店長や上司、本社などに確認しておきましょう。
また、人手が足りない他店への応援として、臨時での別の店舗に出勤するケースも良く見聞きしますが、従事登録していない店舗での業務時間はカウントされません。また、複数店舗での従事登録も、同じ会社の店舗なら可能ですが、2つ以上の都道府県において従事登録を申請することはできません。
社内の異動などで医薬品販売の業務から離れた期間や、休憩時間や有給休暇、薬事に関する業務以外の勤務時間も、実務(業務)経験としてカウントできないので注意しましょう。
離職期間は3年以上空けないのがベスト
管理者要件を満たす登録販売者が、出産や育児、介護などで離職し、その後、復職する場合にも注意が必要です。仮に4年間離職すると、復職した際にその時点での「過去5年以内に24か月以上」という管理者要件を満たすことができなくなります。
再び管理者要件を満たす登録販売者に戻るまでの間は、「研修中の登録販売者」となってしまいます。
管理者要件を満たす登録販売者の離職期間が3年以内の場合は、復職時点でも業務経験の要件を満たすことができます。離職期間が3年を超えると、復職後に研修中の期間が生じてしまうため、将来的に正規の登録販売者としての復帰を希望する場合は離職期間を3年以内に留めることが重要です。